これからの相続・遺産分割~第4回「相続登記義務化に関連する制度改正」
今回は、前回に引き続き「相続登記の義務化」に伴う諸環境の整備策についてお話しします。
少し細かい話になる部分もありますが、不動産登記制度の目的そのものの変化(拡張)にも関わりますので、ご説明いたします。

【所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示(令和8年4月1日施行予定)】
現行法の下では、不動産の所有権の登記名義人が死亡しても、申請に基づいて相続登記がなされない限り、当該登記名義人が死亡した事実は不動産登記簿に公示されないので、登記記録から所有権登記名義人の死亡の有無を確認することはできません。
これに対しては、民間事業等の計画段階等においてその確認が可能であれば、事業用地の選定が円滑となることが期待されることから、登記名義人の死亡情報をできる限り登記に反映させるべきであるとの指摘がなされています。
そこで、改正法(改正不登法第76条の4)では、登記官(法務局)が、他の公的機関(いわゆる「住基ネット」等が想定されています。)から取得した所有権の登記名義人の死亡情報に基づいて不動産登記に死亡の事実を符号によって表示する制度が新設されます。
【住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月1日施行予定)】
以下ご説明する各整備策は、相続登記の義務化そのものの内容とは異なる面がありますが、所有者不明土地の発生予防の観点では共通する点があることから、ご説明いたします。
所有権の登記名義人が住所等を変更してもその旨の登記がされない原因としては、
①現行法上、住所等の変更登記の申請は任意とされており、かつ、変更をしなくても特に不利益はないこと、
②転居等の度ごとにその所有する不動産についてそれぞれ変更登記をするのは煩わしいことが挙げられます。
そこで、改正法(改正不登法第76条の5、第164条第2項)では、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更があった日から「2年」以内にその変更登記の申請をすることを義務付けるとともに、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、「5万円」以下の過料に処することとされます。
【職権による住所等の変更登記(令和8年4月1日施行予定)】
前記した住所等の変更登記の申請義務化に伴い、その手続の簡素化・合理化を図る観点から、登記官が住基ネット(自然人の場合)や商業・法人登記のシステムから必要な情報を取得し、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認める場合には、職権で住所等の変更登記を行うこととなります(改正不登法第76条の6)。
ただし、自然人については、例えばDV被害者等であって最新の住所を公示されることに支障がある方も存在しうることや、個人情報保護の観点も考慮に入れなければならないことは、容易に想像できます。
そこで、法務局側から、事前に所有権の登記名義人に変更登記をすることについて確認を行い、登記名義人から変更についての了解(法文上は「申出」)を得たときに登記官が職権的に変更登記をすることとされます(改正不登法第76条の6但書)。
【海外居住者の連絡先の登記事項化(令和6年4月1日施行)】
所有権の登記名義人が、国内に住所を有しないときは、国内の連絡先を登記する必要があるとされました。連絡先としては、第三者(個人または法人)を指定することができ、その氏名若しくは名称又は住所が登記されます(改正不登法第76条の2第1項第2号)。海外居住の日本人や海外投資家が増えるなかで、所有者の確認や連絡を容易にするために導入されました。なお、当面の間、「連絡先なし」とする登記も許容されることから、実効性については、今後の運用を注視する必要があると思います。
(著者:司法書士 大谷)
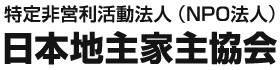

 03-3320-6281
03-3320-6281
