不動産投資にも欠かせない金融リテラシーの重要性
金融リテラシーとは、お金に関する知識や能力のことで、預貯金や、保険、ローンや投資に関する仕組みを理解し、その知識や能力を高めることにより、資産形成に役立つことはもちろんのこと、投資詐欺などのお金のトラブルを防衛することにつながります。

警察庁の発表によると、2024年の特殊詐欺、投資詐欺、ロマンス詐欺などによる詐欺被害の総額は、なんと約2,000億円に上るそうです。
日本にはお金をたくさん持っている人がいるということに感心するとともに、これほどテレビや新聞やネットなどのあらゆるメディアで詐欺被害防止を啓蒙しても被害が増え続ける現実をみれば、残念ながら詐欺は永遠に無くならないといえるでしょう。また、詐欺とは言えないまでも、もう少し自分に知識があれば防げたであろう金銭トラブルや投資の失敗など、お金にまつわるトラブルはあげたらきりがありません。このような失敗をしないためには、冒頭に述べた通り、お金の基礎や金融の仕組みを理解し、自分で考える癖をつけることが重要となります。
これが金融リテラシーを高める。ということです。金融リテラシーを高めることは、投資詐欺などの被害予防になることに加えて、自らの資産形成の役に立つことは間違いないでしょう。
不動産分野においても賃料収入を目的とした不動産投資をはじめ、不動産特定共同事業法を活用した小口化商品、不動産投資信託、いわゆるリート(REIT)など、金融商品としての側面も高くなり、不動産知識はもちろんのこと、より金融リテラシーが求められる時代になったといえます。
不動産投資の指標となるのは投資利回りです。投資利回りとは投資金額、要するに購入金額に対する賃料収入の割合です。同じ金額を投資すると考えた場合、利回りが高ければ収入が多くなりますし、利回りが低ければ収入は低くなります。当然、利回りが高い方がいいと考えがちですが、そこには利回りに比例した不動産特有のリスクが伴うことを忘れてはいけません。リスクとは、危険度や不確実性といいますが、心配事、不安要素と言ってもいいかもしれません。要するに不安要素が高ければ利回りは高くなり、不安要素が少なくなれば利回りは低くなります。いわば不安要素を利回りで補っているともいえます。
不動産はその特性からたくさんのリスク、つまり不安要素を抱えています。
不安要素の一例をあげると、投資した金額が将来にわたって保証されていないという事です。要するに将来、売却しようとした場合に、購入金額より高く売れる場合もあれば安くなる場合もあり、投資した元本が保証されていないということです。身近な例を挙げると、預貯金は、最近になってやっと金利が少し上がったとはいえ、利息は雀の涙ほどです。しかし、預け入れられた元本は保証されているので、リスク(不安要素)はほぼゼロと言っても過言ではありません。これが元本の保証されている預貯金と、保証されていない不動産との大きな違いであり、利息、利回りの違いです。金融リテラシーのイロハのイですが、最近では安心して預けたはずの銀行に財産を盗まれるなんてことも起きており、プロのリテラシーというよりモラルが問われているところです。まさに泥棒に財産を預けていたという笑えない話ですね。
(著者:不動産コンサルタント 伊藤)
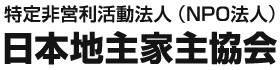

 03-3320-6281
03-3320-6281
