第3回「相続登記義務化~その3」
今回は、「相続登記の義務化」に伴う諸環境の整備策についてお話しします。
相続登記の申請義務化の実効性を確保するために「相続人申告登記」という新たな登記が設けられた点については、前回ご説明したとおりです。その他の措置として、以下のものがあります。

【相続登記の登録免許税の免税措置について~その1】
まず、相続(遺贈を含みます)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権移転登記を受ける前に死亡した場合には、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするするために受ける登記については登録免許税(登記申請の手数料として納付する税金)を課さないこととされました。
具体例としては、ある土地に関し、A(登記名義人)が死亡し、まずBが相続し(一次相続)、その後、Bが死亡し、C(申請人)が相続した場合です。
このような場合、C(申請人)は、一次相続(AからB)について相続登記を申請するとともに、二次相続(BからC)について相続登記を申請することで最終的に当該土地がC名義となりますが、この一次相続(AからB)についての相続登記に関する登録免許税が免除されるという措置です。
なお、この免税措置については、必ずしもCがその土地を相続している必要はなく、Bが生前にその土地を第三者に売却していたとしても、一次相続についての相続登記の登録免許税は免税となります。
【相続登記の登録免許税の免税措置について~その2】
次に、土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、その登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額(課税明細や固定資産税評価証明書に記載されている価額)が100万円以下であるときは、その土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税が免除されるという措置です。
その1、その2ともに、相続登記に係る登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%ですが、これが免除されます。当該措置は、一応、今年(令和7年)の3月31日迄とされており、現時点では、次年度からの扱いにつき正式な発表はされていませんが、相続登記推進の見地からすると、延長される可能性が高いものと思われます。
なお、これらの免税措置を実際に受けるためには、登記申請書に免税の根拠となる租税特別措置法の該当条文を具体的に示して申請する必要があり、これが記載されていない場合に法務局から指摘されることはありませんし、登記申請後に申し出ても、還付を受けることはできず、結局免税措置を受けられない点に注意する必要があります。
【所有不動産記録証明制度(仮称)(令和8年2月2日施行予定)】
相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるよう、登記官において、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられます。
現在、被相続人名義の不動産の調査方法としては、毎年、登記名義人に送られてくる納税通知書・課税明細で確認する方法があります。しかし、ここには、非課税の不動産は記載されないため、私道部分は記載されず、この部分を見落とす危険があります。
そのため、名寄帳を取り寄せることで、非課税の不動産を確認する作業が必要となる場合があります。しかし、名寄帳は自治体ごとにしか調査することができず、被相続人が生活の本拠であった土地と全く関係のない自治体に属する不動産を所有していた場合にこれらを調査するのは非常に困難となります。
この点、所有不動産記録証明制度(仮称)を利用すれば、被相続人名義の土地を全国から、課税・非課税の別なく探すことが可能となり、相続登記の対象となる不動産を容易に把握することが可能となり、相続登記申請義務化の実効性確保に寄与することが期待されています。
(著者:司法書士 大谷)
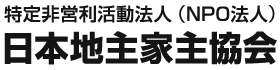

 03-3320-6281
03-3320-6281
