これからの相続・遺産分割~第5回「番外編・検索用情報の申出について」
【「検索用情報の申出」ってなに?】
今回は、「番外編」と称して、令和7年4月21日から開始された「検索用情報の申出」についてご説明いたします。
これは、前回ご説明した、令和8年4月1日施行予定の「職権による住所等の変更登記」(いわゆる「スマート変更登記」)の開始に先立ち、新たに導入される制度です。
同日以降、新たに自然人が所有権保存登記や所有権移転登記を申請することによって所有権登記名義人となる場合、原則として、その登記申請時に検索用情報を申し出ることが必要となります。

検索用情報とは、具体的には「氏名、氏名のふりがな(外国人にあってはローマ字氏名)、住所、生年月日、メールアドレス」を指します。検索用情報の申出を行うと、当該物件の登記情報と検索用情報が法務局のシステム内部に記録されます。
この記録が完了したときは、申出のあったメールアドレス宛に、次に掲げる事項
(①申出手続きが完了した旨、②立件の年月日及び立件番号、③不動産番号、④認証キー、⑤申出を受けた登記所の表示)
を記録した電子メールが送信されます。
なお、④認証キーとは、メールアドレス(登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先)を変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号です。
なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合は、その旨を申請情報の内容とします。この場合、登記官が職権で住所等変更登記を申請することの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することが想定されています。
一方、既に所有権の登記名義人である者についても、検索用情報の申出をすることができます。
留意すべき点は、職権による住所等変更登記の対象となる不動産は、検索用情報の申出をした不動産に限られるという点です。申出をした不動産以外に所有する不動産があった場合は、当該不動産について改めて検索上情報の申出をすることによって、職権による住所等変更登記の対象とすることができます。
また、あくまでも検索用情報なので、登録したメールアドレスや生年月日が登記される事はありませんので、この点はご安心下さい。
【検索用情報を用いた職権による住所等の変更登記の流れ】
次に、検索用情報を用いてどのように職権による住所等の変更登記が行われるのかをご説明いたします。
登記官は、検索用情報(ここでは、上記のメールアドレス以外のもの)を用いて、住基ネットの住民票情報に定期的に照会をします。
そして、個人(自然人)が住所等の変更を役所に届け出ると、住基ネットから氏名・住所の変更情報が提供され、登記官が氏名・住所の変更情報を取得します。
氏名・住所の変更情報を取得した登記官は、職権で変更登記をすることについて、登記名義人に意思確認をします。この際に用いられるのが、前述したメールアドレスです。メールアドレスがない旨の申出がされている場合は、書面による意思確認をします。
この意思確認に対し、登記名義人が了解をすると、職権による変更登記が行われ、これにより、住所等変更登記義務は履行済みとなり、当該義務違反による過料の対象からは除外されます。
今後、司法書士に登記を依頼する際、今までそんなこと聞かれたことなかったのに「メールアドレス教えて下さい」とお願いされるようになるかと思いますので、ご協力頂ければ幸甚です。
(著者:司法書士 大谷)
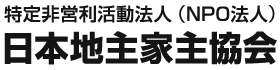

 03-3320-6281
03-3320-6281
